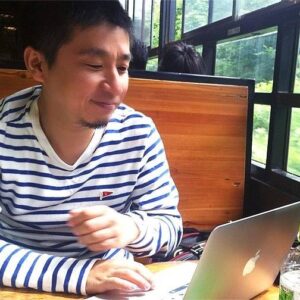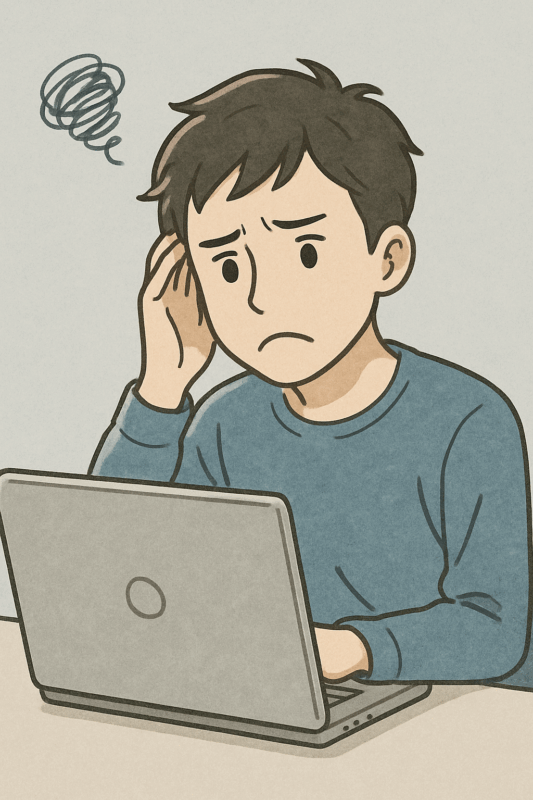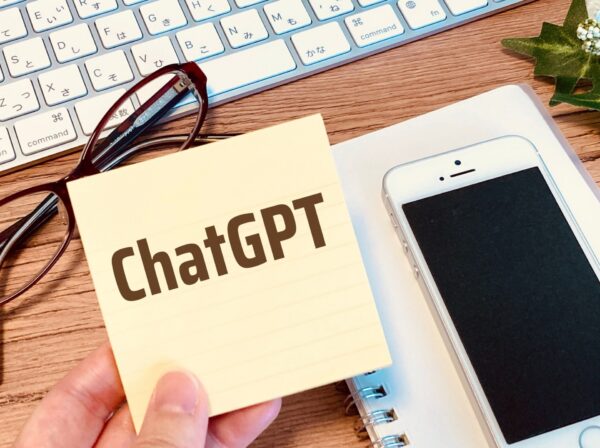安売りはいけません。
100円では儲からない商品を
100円で売ってはいけません。
少なくとも、儲かる価格で売りましょう。
今回は、安売りに頼らず、価値を高めるヒントをご紹介します。
安売りしないこと
安売りしてはいけない。
ほとんどの社長さんはこのことを理解されています。
それでも状況によっては、
安売りしてしまいます。
自分がそういう状況に陥っているとき、
ほんとに困ってしまいますね。
価格競争に巻き込まれない
安売りしてしまうと
価格競争に巻き込まれてしまいます。
価格競争に巻き込まれてしまうのは避けたいところです。
価格競争に参加するのではなく、自社の商品やサービスの独自の価値をしっかりと打ち出すことは、特に中小企業にとってとても重要な戦略です。
安く売ることで一時的にはお客さんを集められるかもしれませんが、もし他のお店がもっと安く売り始めたら、そちらにお客さんが移ってしまいます。
つまり、安い価格での競争に勝っても、それは一時的なもので、お客さんとの長いお付き合いにはつながらないんです。
価格競争は体力勝負
価格競争は体力勝負みたいなもので、大きな会社ならいいです。
ですが、中小企業が長く続けるのは難しいです。価格は、他の会社も真似しやすいので、赤字覚悟で安くする会社も出てくるので、ずっと安い価格を保ち続けるのは大変です。
自分たちの商品を特別なものに
価格だけに頼らず、自分たちの商品やサービスがどう特別なのかをしっかりお客さんに伝えることが大切だなぁと思います。
自分たちの商品やサービスの特徴や、お客さんにとっての価値を伝えることで、お客さんは価格だけでなく、その商品やサービスの特別な価値のためにお金を払ってくれるようになります。
価格競争を避けるために
いかに安く売るかより、いかに安く売らずに済むか
中小起業は、「いかに安く売るか」より、「いかに安く売らずに済むか」を考えるべきですよね。
顧客が感じる品質を上げたり、ブランド力を強化したり、独自性を出したり、代替品が少ない商品を扱ったりすることが大事。
安売りがダメな理由
安売りに頼るビジネス戦略は、一見すると魅力的な短期的解決策に思えます。
けれども、この戦略は実はリスクも大きいです。
安売りを続けると、お客さんはその商品やサービスの本当の価値を見失ってしまう可能性があります。安売りが当たり前になってしまい、その商品やサービスの特徴や品質、ブランドの価値が見えにくくなるんです。
長期的に見ると、常に安い価格で商品を提供し続けることは、会社にとって大きな負担になります。
利益が少なくなるため、商品の品質を維持したり、サービスを改善したり、新しい商品を開発したりするための資金が不足することもあります。
ブランディングは、ただ商品やサービスを提供する以上のことを意味します。それは、お客さんとの間に特別な感情的なつながりを築く過程です。この過程では、お客さんがそのブランドを選ぶ理由を作り出します。
それは、商品の品質や特徴だけでなく、ブランドが代表する価値観、ストーリー、体験によっても形成されます。
安売りは、短期的な売上を作ることはできるかもしれませんが、長期的にみると、顧客の心のなかにあるブランド価値を著しく低下させてしまいます。
このような戦略は会社の評判を傷つけ、長期にわたってブランドイメージにネガティブな影響を及ぼす可能性が高いのです。
確かに、顧客は良い商品をできるだけ安く手に入れたいと考えます。しかし、それは一時的な満足に過ぎず、長期的には品質、信頼性、サービスといった要素が顧客の忠誠心とブランドの評判を決定します。
安売りは企業の価値を低下させ、結果的にブランドの独自性や魅力を損なうことに繋がります。
では、どのようにすれば良いのでしょうか?
価格ではなく価値に投資することで、企業は独自のブランドを創造し、市場での独特な位置を確立することです。
なぜ安売りをしたくなるのか?
安売りには、特別なお得感の魔力がある
「特売」「セール」「特価」「格安」といった言葉が、私たちに大きな影響を与えるのは、これらの言葉が単に価格の安さを伝えるだけではありません。
こうした言葉には、ただの数字以上の何か、つまり「特別なお得感」が含まれています。これは消費者の心の中にある「お買い得」という感覚を刺激し、購買意欲を高める効果がああるのです。
「特売」という言葉は、私たちをだまします。「得」ではない商品まで購入させてしまうからです。
私たちは、商品の情報を処理する際、自分にとって重要な情報には重きを置き、そうでない情報には軽く扱います。
「特売」という情報は通常、商品の総合評価を高める効果があります。
「特売」という言葉は、私たちが良い気分になるよう仕向け、その結果、より購買に傾くように作用します。
結局のところ、「特売」「特価」「格安」などの言葉は、消費者の購買行動に強い影響を与えるのは事実です。
しかし、これらの言葉の魅力に惑わされず、賢い選択を心がけることが、賢い消費となることでしょう。
安売りと手ごろな値段は違う
「お得な価格」と「手頃な値段」という言葉は、両方とも価格に関する表現ですが、そのニュアンスには確かに違いがありますね。
「お得な価格」という言葉は、通常の価格よりも明らかに安い場合や、何か特別なプロモーションやセールが行われている時によく使われます。
これは、購入者が通常よりも少ないお金で同じ価値を得られる、つまり「得をする」と感じられるような状況を指します。
たとえば、普段は10,000円する商品がセールで7,000円になっている時など、明らかに価値に対して支払う金額が少なくなっている状況です。
一方で、「手頃な値段」という言葉は、商品やサービスの価格が一般的に受け入れられる範囲にあると感じられる時に使われます。これは特別なセールや割引がなくても、その価格自体がもともと高くない、または購入者にとって無理なく支払える範囲にあることを意味しています。
たとえば、日用品やカジュアルなレストランの食事など、日常的に購入するものに対して使われることが多いです。
要するに、「お得な価格」は価格の割引やセールに焦点を当て、購入者が特別な機会に利益を得ることを強調するのに対し、「手頃な値段」は元々の価格設定が購入者にとって負担にならない水準にあることを指していると言えます。
それぞれの表現は異なる状況や目的に応じて使い分けることができ、購入者の価値観や購入意欲に訴えかけるポイントが異なります。
安売りしなくても売れる方法
ブランドの価値を高めることは、長期的な成功のための重要なステップです。
以下に、商品やサービスの価値を高め、適正価格で提供するための代表的な方法を紹介します。
1、ターゲットをせまくする
ターゲットをしぼることで、その狭いニーズに合わせた商品を提供し、結果的により高い価値を顧客に感じてもらうことができます。
この手法は「ニッチマーケティング」とも呼ばれ、競争が激しい市場や多様なニーズが存在する現代において、効果的な戦略とされています。
「お客を選ばない店は、お客さまからも選ばれない」という言葉は、非常に印象的です。これは、全ての人にアピールしようとすると、結局は誰からも心から支持されないリスクがあるということを意味しています。
2、専門性を深める
特定の分野で詳しくなると、その分野の専門家として広く認知されるようになります。
たとえば、「卵かけ専用しょうゆ」などのような商品は、特定のシーンや目的に合わせて作られています。
特定の使い方をする人にとって、これらの商品は大きな魅力があると感じられます。
これらの商品は普通の商品とは違って、特定の使い方をするために作られているので、そのニーズにぴったり合うものが他にあまりないため、値段が少し高くても選ばれやすくなります。
3、見た目を変える
商品やサービスの価値を高めるためには、見た目を変えるという手法もあります。
パッケージや包装を変えてみる
パッケージや包装は商品の「顔」のようなものです。高級感があるものや、特別なデザインを用いることで、商品の印象を大きく変え、顧客の購買意欲を高めることができます。
商品のサイズを変えてみる
商品のサイズを変えることで、異なる使用シーンを提案したりすることができます。
たとえば、大容量パックは家族向けや頻繁に使用する顧客に魅力的であり、一方で小さなサイズは試しやすく、一人暮らしの顧客や持ち運びを重視する顧客に適しています。
名前を変えてみる
商品やサービスの名前は、その印象を大きく左右します。魅力的で印象に残る名前は、話題性を生み出しますし、特徴や価値を表現する名前を選ぶことで、顧客の関心を引きつけることができます。
4、場所を変える
商品の価値は、それが売られている環境によっても大きく変わります。
同じ商品でも、どこで売られているかによって、人々の感じる価値や設定される価格が異なります。
例えばコーヒーの例は、そのことをとてもよく表しています。
カジュアルなチェーン店のカフェだと200円、手軽に立ち寄れるコンビニだと100円で買えますが、高級感漂うホテルのラウンジで飲むコーヒーは1500円もすることがあります。
これは、ただ単にコーヒーを飲むという行為だけでなく、その場の雰囲気、サービスの質、ブランドイメージなど、商品自体以外の要素が価値に影響を与えているからです。
つまり、商品自体の質も大切ですが、それをどのような環境で、どのように提供するかも商品の価値を大きく左右する要素になるのです。
この原則を利用して、自分の商品やサービスの価値を高めるためには、下のようなアプローチが考えられます:
店舗や販売環境の改善
店内のデザイン、照明、音楽など、購入体験に影響を与える要素を見直し、より魅力的な環境を作り出します。
顧客サービスの向上
スタッフの教育を徹底し、顧客に対する接客態度やサービスの質を高めることで、商品の価値を高めます。
ストーリーテリングの導入
商品や店舗に関連する背景や物語を顧客に伝えることで、感情的なつながりを作り、価値を高めます。
まとめ
今回は、安売りに頼らず、価値を高めるヒントをご紹介しました。
価値を高めるには、さまざまアイデアや知恵を集めて案を作成し、それらを長期的に実践することが必要です。
そのためには専門家に相談するのが近道です。弊社は、無料から集客のご相談を承っています。
- インターネットを使った集客方法を知りたい
- 集めた知識を整理したい
など、お気軽にご利用ください。