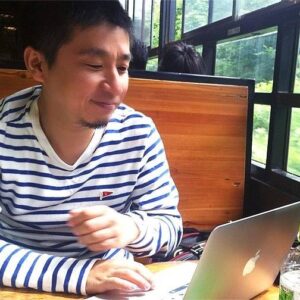「専門的な記事をしっかり書いているのに、なぜか読者の反応が薄い」
「正確で詳細な情報を提供しているのに、問い合わせが来ない…」
「同業者からは評価されるのに、一般のお客様には響かない…」
そんな悩みを抱えているあなた、もしかすると専門用語を使いすぎていませんか?
こんにちは、つちやたけしです。今日は多くの専門家が無意識に犯してしまう「専門用語過多の罠」について詳しくお話しします。
専門用語ばかり使った記事は、どんなに正確で価値のある情報でも、読者を遠ざけてしまい、集客効果を大幅に下げてしまう危険性があります。
専門用語が多すぎると、集客のあらゆる場面でマイナスが起きてきます。
LPの文章もそうです。→LP作成でよくある失敗談として専門用語が多いと集客できません。
多くの専門家が陥る「専門用語が多すぎる」パターン
私がコンサルティングで実際に出会った典型的なパターンをご紹介します。
パターン1:業界用語を当たり前のように使用
• 専門用語の説明なしにいきなり使用
• 読者が理解できて当然という前提
• 用語の意味よりも使うことが目的化
• 「プロっぽく見える」という勘違い
例(税理士のブログ): 「青色申告特別控除を適用するためには、複式簿記による記帳が必要です。貸借対照表と損益計算書を作成し、e-Taxまたは電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。」
→ 一般の個人事業主には理解困難
パターン2:略語・専門略称の多用
• 業界内では常識の略語を多用
• 略語の正式名称や意味を説明しない
• 読者が調べる手間を考慮していない
• 文章がアルファベットだらけになる
例(Webマーケティング): 「SEOの効果を高めるには、CTRとCVRを改善し、UIとUXを最適化する必要があります。GAでKPIを設定し、PDCAサイクルを回しましょう。」
→ 初心者には暗号にしか見えない
パターン3:法律・制度用語の羅列
• 法的な正確性を重視するあまり条文用語を多用
• 一般用語への言い換えを行わない
• 読者にとっての意味や影響を説明しない
• 堅い印象で親しみにくい
パターン4:技術用語・カタカナ語の氾濫
• 新しい技術や手法をカタカナ語で説明
• 日本語での説明を省略 • 読者の知識レベルを考慮しない
• 「最新」をアピールしたい気持ちが先行
なぜ「専門用語ばかり」使ってしまうのか?
理由1:「専門性をアピールしたい」という欲求
「専門用語を使うことで、自分の専門性や知識の深さを示したい」という気持ちが働きます。
しかし、これは完全に逆効果。専門性は専門用語の多さではなく、複雑なことをわかりやすく説明できる能力で示されるのです。
理由2:「業界の常識」という思い込み
長年その業界にいると、専門用語が日常語になってしまい、一般の人が知らないということを忘れてしまいます。
「これくらいは知っているだろう」という思い込みが、読者との距離を生んでしまいます。
理由3:「正確性を重視したい」という真面目さ
「専門用語を使わないと、正確な情報を伝えられない」という真面目な考えから、専門用語に頼ってしまいます。
しかし、正確でも理解されない情報は、結果的に価値がありません。
理由4:「簡単に説明する方法がわからない」
専門用語を使わずに説明することの難しさから、つい専門用語に逃げてしまいます。
実は、わかりやすく説明することこそが、真の専門性の証明なのです。
専門用語が多すぎると、引き起こる問題
問題1:読者の離脱
専門用語だらけの記事は、読者にとって「読む価値がない」と判断されてしまいます。
離脱プロセス
- タイトルに興味を持ってクリック
- 冒頭から専門用語が連発
- 「難しすぎて理解できない」と感じる
- 「自分には関係ない記事だ」と判断
- 即座に離脱
実際の調査では、専門用語が多い記事の直帰率は85%を超えています。
問題2:専門家としての信頼失墜
「専門用語を使いこなす = 専門家」という認識は間違いです。
現代の読者が求める専門家像
• 複雑なことをわかりやすく説明できる人
• 読者の立場に立って考えてくれる人
• 親しみやすく相談しやすい人
• 実用的で役立つアドバイスをくれる人
専門用語ばかり使う専門家は「頭でっかちで実用性がない」と思われてしまいます。
問題3:検索エンジンからの評価低下
Googleは「ユーザーにとって価値のあるコンテンツ」を高く評価します。
SEOへの悪影響: • 読者の滞在時間が短い • 直帰率が高い • 検索意図にマッチしていない • ユーザビリティが低い
結果として、検索順位が下がり、オーガニック検索からの流入が減少します。
問題4:ターゲット読者とのミスマッチ
あなたのサービスを必要としている人の多くは、専門用語を理解しない一般の方です。
問題5:口コミ・紹介機会の完全損失
専門用語だらけの記事は、読者が「誰かに教えたい」と思わない内容になってしまいます。
口コミが起こらない理由
• 内容を理解できないので説明できない
• 友人に勧めても理解してもらえない
• 「役に立った」という実感がない
• シェアしても価値を提供できない
読者が本当に求める「わかりやすさ」とは
読者が求める説明の特徴
具体性
• 抽象的な概念を具体例で説明
• 身近な例えや比喩を使用
• 数字や事例を用いた明確な説明
• 「つまり、こういうことです」という要約
段階性
• 基本から応用へ順序立てて説明
• 前提知識から丁寧に解説
• 一度に多くの情報を詰め込まない
• 読者のペースに合わせた展開
視覚性
• 図解や表を効果的に使用
• 文字だけでなく視覚的にも理解しやすく
• 色分けや強調で重要ポイントを明示
• ステップバイステップの流れ図
実用性
• 読者の日常生活に関連付けて説明
• 実際に使える情報として提供
• 「で、結局どうすればいいの?」に答える
• アクションにつながる内容
専門用語をわかりやすく言い換える7つの方法
方法1:身近な例えで説明する
複雑な概念を、読者が知っている身近なものに例えて説明します。
方法2:専門用語の後に括弧で説明を追加
専門用語を使う必要がある場合は、すぐに説明を付け加えます。
例: 改善前: 「SEO対策が重要です」
改善後: 「SEO対策(検索エンジンで上位表示されるための工夫)が重要です」
方法3:専門用語を使わずに説明し直す
専門用語を全く使わずに、同じ内容を一般的な言葉で表現します。
例: 専門用語: 「相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数です」
言い換え: 「相続税は、亡くなった方の財産が一定額を超えた場合にかかる税金です。この『一定額』は、家族の人数によって決まり、例えば夫婦と子供2人の家族なら5,400万円までは税金がかかりません」
方法4:ストーリー形式で説明する
実際のケースや物語を使って、専門的な内容をわかりやすく伝えます。
例: 専門用語: 「遺産分割協議書の作成には相続人全員の署名・押印が必要です」
ストーリー: 「田中さんのお父さんが亡くなったとき、残された家族(お母さんと田中さん、弟さん)は、お父さんの財産をどう分けるかを話し合いました。この話し合いの結果を『遺産分割協議書』という書類にまとめ、家族全員が署名・押印することで、正式な取り決めとなります」
方法5:図解・イラストを活用する
文字だけでは理解しにくい専門的な内容を、図やイラストで視覚的に説明します。
効果的な図解例
• 手続きの流れ図
• 組織図、相関図
• before/afterの比較図
• チェックリスト形式の整理
方法6:Q&A形式で読者の疑問に答える
読者が抱きそうな疑問を想定し、Q&A形式で専門用語を解説します。
例: Q:「青色申告」って何ですか?白色申告との違いは?
A:青色申告は、より詳しい帳簿をつける代わりに税金が安くなる制度です。例えば、年収400万円の個人事業主の場合、青色申告にすることで約10万円の節税効果があります。白色申告は簡単ですが、この節税メリットはありません。
方法7:段階的に詳しく説明する
最初は簡単に、その後徐々に詳しく説明していく構成にします。
構成例
- 一言での要約:「○○とは、簡単に言うと△△のことです」
- 基本的な説明:一般的な言葉で基本概念を説明
- 具体例:実際のケースで理解を深める
- 詳細解説:必要に応じて専門的な内容を補足
- まとめ:要点を再確認
わかりやすさこそが専門家の真価
専門用語ばかり使った記事は、どんなに正確で詳細な情報でも、読者を遠ざけてしまい、集客効果を大幅に下げてしまいます。
しかし、逆に言えば、複雑な専門内容をわかりやすく説明できることこそが、現代の専門家に求められる最も重要なスキルなのです。
私自身、20年間のWebマーケティング経験で学んだ重要な教訓は、「わかりやすさこそが専門家の真価を示す」ということです。
今すぐ始めるべき4つのアクション
- 専門用語チェック:現在の記事の専門用語使用状況を客観的に評価
- 専門用語リスト作成:よく使う用語とその一般用語説明を整理
- 記事リライト計画:重要記事から順次わかりやすく修正
- 作成ガイドライン策定:今後の記事作成でのわかりやすさ基準を設定
この改善により、あなたのブログは確実に変わります。
• 読者の滞在時間の大幅な向上
• 直帰率の劇的な改善
• 問い合わせ率の大幅増加
• 専門家としての親しみやすさ向上
• 口コミ・紹介の自然発生
「でも、専門用語を使わないと正確性が失われるのでは?」
そう心配する方もいるかもしれません。しかし、正確でも理解されない情報は、結果的に何の価値も生みません。
本当の専門家とは、複雑なことを誰にでもわかるように説明できる人なのです。
今日から、あなたのブログを「専門的だけど親しみやすく、誰にでもわかりやすい情報源」に変えていきましょう。
その第一歩は、「読者の立場に立って、相手のレベルに合わせた説明を心がける」ことから始まります。
わかりやすいブログは、読者との距離を縮め、信頼関係を築き、最終的に「この人になら安心して相談できる」と思ってもらえる最強のツールになるのです。