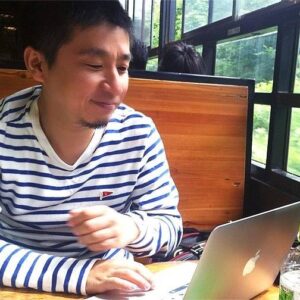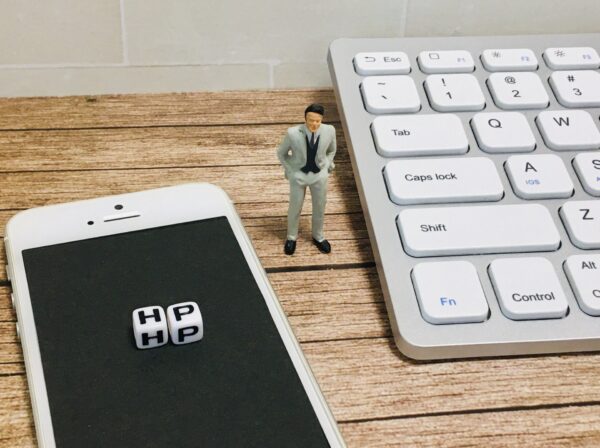「ブログを始めたときは毎日更新するつもりだったのに、気がついたら1ヶ月も放置している…」
「最初の頃はやる気満々だったのに、だんだん書くネタがなくなって更新が止まった…」
「忙しさを理由にブログを後回しにしていたら、いつの間にか半年も更新していない…」
そんな状況に陥っていませんか?
こんにちは、つちやたけしです。今日は多くの事業者が挫折してしまう「継続性」について詳しくお話しします。
継続性のないブログは、どんなに最初に素晴らしい記事を書いたとしても、集客力を大幅に失ってしまい、最終的には完全に見放されてしまう危険性があるのです。
多くの事業者が陥る「継続できない」パターン
私がコンサルティングで実際に出会った典型的なパターンをご紹介します。
パターン1:最初から高すぎる目標設定
• 「毎日更新する!」と意気込んで始める
• 1記事2,000字以上を目標にする
• 完璧な記事を書こうとして時間がかかりすぎる
• 現実とのギャップに挫折してしまう
例:「毎日5,000字の専門記事を書いて、1年で365記事投稿する!」 → 3週間で挫折
パターン2:ネタ切れによる更新停止
• 最初は書きたいことがたくさんあった
• しかし1ヶ月もすると「何を書けばいいかわからない」状態に
• 「良い記事が思い浮かばない」と更新を先延ばし
• 結果的に長期間の更新停止
例:開始3ヶ月で「もう書くことがない…」
パターン3:忙しさを理由にした後回し
• 「今日は忙しいから明日書こう」
• 「今週は無理だから来週まとめて書こう」
• 気がついたら1ヶ月、2ヶ月と放置 • 復帰するタイミングを失ってしまう
例:「来月から本格的に再開する」が口癖になる
パターン4:結果が出ないことへの焦りと諦め
• 3ヶ月書いても問い合わせが来ない
• アクセス数が思うように伸びない
• 「ブログなんて意味がない」と諦めてしまう
• 効果が出る前に辞めてしまう
例:「半年やったけど効果なし、やめよう」
なぜ「継続できない」のか?
理由1:「完璧主義」の呪縛
多くの人が「質の高い記事を書かなければならない」というプレッシャーを自分にかけてしまいます。
しかし、完璧を求めすぎると: • 1記事にかかる時間が長すぎる • 「もっと良い内容にしなければ」と公開を先延ばしする • 結果的に更新頻度が下がり、継続できなくなる
実際には、80点の記事を継続することの方が、100点の記事を月1回書くよりもはるかに効果的です。
理由2:「結果への過度な期待」
「ブログを始めれば3ヶ月で集客できる」 「毎日更新すれば半年で成果が出る」
こうした過度な期待が、現実とのギャップを生み、継続への意欲を削いでしまいます。
実際には、ブログの効果が本格的に現れるまでには1年以上かかることが多く、短期間で結果を求めすぎると必ず挫折します。
理由3:「ルーチン化」の不足
継続できない人の多くは、ブログ運営を「気分」や「やる気」に依存しています。
• 「やる気が出たら書こう」
• 「時間ができたら更新しよう」
• 「良いネタが思い浮かんだら投稿しよう」
しかし、これらは全て不安定な要素です。継続するためには、気分に左右されない仕組み作りが必要です。
理由4:「孤独感」と「相談相手の不在」
ブログ運営は基本的に一人で行う作業のため、孤独感を感じやすく、相談できる相手もいないことが多いです。
• 「本当にこの方向性で良いのか?」 • 「なぜアクセスが増えないのか?」 • 「このまま続けて意味があるのか?」
こうした疑問や不安を一人で抱え込むことで、継続への意欲が失われてしまいます。
継続性のないブログが引き起こす問題
問題1:読者からの信頼が失墜
更新が止まったブログは、読者から「もう更新されないサイト」と判断されてしまいます。
読者の心境変化
• 最初の訪問:「面白そうなブログを見つけた」
• 2回目の訪問:「あれ?新しい記事がない」
• 3回目の訪問:「まだ更新されていない…」
• その後:「このサイトはもう見ない」
一度失った読者の信頼を取り戻すのは非常に困難です。
問題2:検索エンジンからの評価低下
Googleは「フレッシュネス」(情報の新しさ)を重要な評価要素の一つとしています。
継続性がないことによるSEOへの悪影響
• サイト全体の評価が徐々に下がる
• 既存記事の検索順位も低下する
• インデックス数が下がる
• 結果的にオーガニック検索からの流入が激減
実際の事例では、1年間更新を停止したブログのアクセス数が70%減少したケースもあります。
問題3:競合他社との差が決定的に拡大
あなたが更新を止めている間にも、競合他社は継続的に情報発信を続けています。
競合との差の拡大
• 専門性の差:継続する競合は知見を蓄積し続ける
• 認知度の差:定期的な発信で存在感を維持
• 信頼度の差:継続性が信頼性の証明となる
• 集客力の差:継続するサイトに読者が集中
一度開いた差を埋めるのは非常に困難になります。
問題4:それまでの努力の完全な無駄
継続を止めることで、これまでの投資が全て無駄になってしまいます。
特に、ブログの効果が現れる直前で諦めてしまうケースが多く、「あと少し続けていれば成果が出たのに…」という状況になりがちです。
問題5:ビジネス機会の大量損失
継続性のないブログは、長期的なビジネス機会を大量に失ってしまいます。
失われる機会
• 潜在顧客との接点機会
• 専門家としての認知度向上
• 口コミや紹介の発生
• 新しいビジネスチャンスとの遭遇
これらの機会損失は、短期的には見えにくいですが、長期的には計り知れない損失となります。
継続可能なブログ運営の7つの法則
法則1:現実的な目標設定
継続可能な目標を設定することが最も重要です。
最初は「物足りない」と感じるくらいの目標設定がベストです。継続できるようになってから、徐々にレベルアップしていけば良いのです。
法則2:記事ネタのストック化
「何を書けばいいかわからない」状況を避けるため、事前にネタをストックしておきます。
目安として、常に10-20記事分のネタをストックしておくことをお勧めします。
法則3:執筆時間の固定化
「時間ができたら書こう」ではなく、決まった時間にブログを書く習慣を作ります。
法則4:記事のテンプレート化
毎回ゼロから構成を考えるのではなく、テンプレートを用意して効率化します。
基本テンプレート例
- 導入(読者の悩みを明確化)
- 問題提起(なぜその悩みが生まれるか)
- 解決策(具体的な方法を3-5個)
- 事例(実際のケースで説明)
- まとめ(要点の再確認)
法則5:小さな成功の積み重ね
大きな成果を期待せず、小さな成功を積み重ねることに焦点を当てます。
法則6:仲間やメンターの存在
一人で継続するのは困難なため、仲間やメンターの力を借ります。
外部からの適度なプレッシャーと応援が継続の大きな力になります。
法則7:長期視点での取り組み
短期的な結果にとらわれず、長期的な視点で取り組みます。
継続こそが最強の差別化戦略
継続性のないブログは、どんなに最初に素晴らしい記事を書いても、集客力を大幅に失い、最終的には完全に見放されてしまいます。
しかし、逆に言えば、継続することができれば、それだけで多くの競合他社を大きく引き離し、読者からの信頼と検索エンジンからの評価を同時に獲得することができます。
私自身、20年間のWebマーケティング経験で学んだ重要な教訓のひとつは、「継続こそが最強の差別化戦略」ということです。
今すぐ始めるべき4つのアクション
- 継続状況の評価:過去の更新パターンを客観的に分析
- 現実的な目標再設定:継続可能なレベルでの目標設定
- 継続支援システム構築:時間固定化とネタストック体制の整備
- 挫折防止策の準備:やる気低下時の対応策を事前に用意
この改善により、あなたのブログは確実に変わります。
「でも、継続するのは本当に大変…」
そう思う方もいるかもしれません。しかし、継続の難しさは誰もが感じることです。だからこそ、継続できた人だけが大きな成果を手にすることができるのです。
100点の記事を年に1回書くよりも、80点の記事を週1回書く方がはるかに効果的です。
今日から、あなたのブログを「継続性という信頼の上に築かれた、読者にとってなくてはならない情報源」に変えていきましょう。
その第一歩は、「完璧を求めることをやめて、継続することを最優先にする」ことから始まります。
継続するブログは、時間が経つほど、積み重ねが大きくなるほど、その価値と影響力を指数関数的に増大させていきます。そして最終的に、あなたを業界でなくてはならない存在へと押し上げてくれるのです。