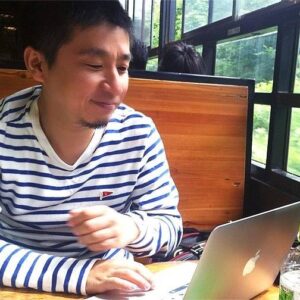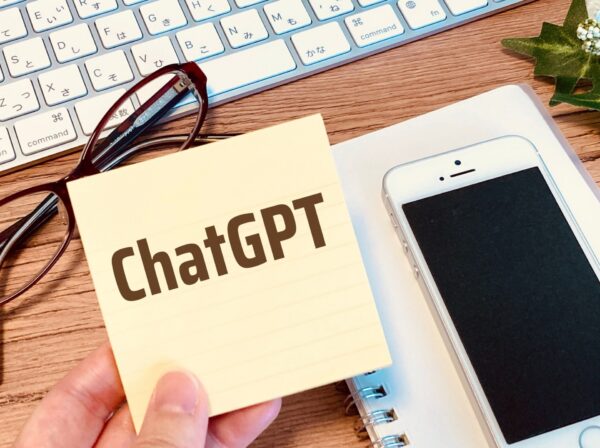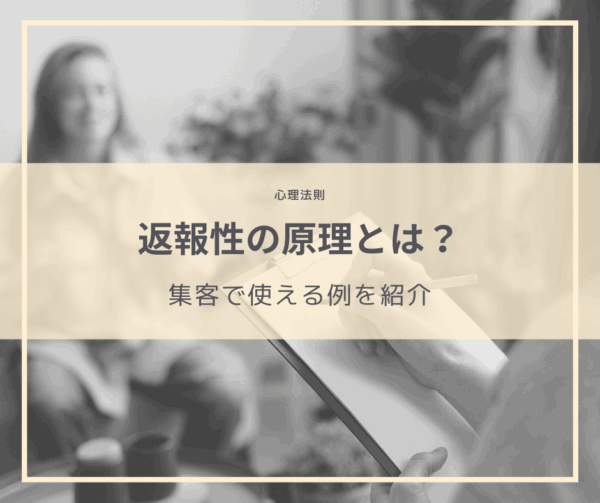「提案書は素晴らしかったのに、納品物がまったく期待外れ…」
そんな失敗を経験したことはありませんか?
突然ですが、、、、「営業の口がうまい制作会社」ほど、危険です。
立派な理論を語り、専門用語を並べ、さも凄腕のように見せかける。
しかし、実際に発注してみると
「実現できない」
「約束が守られない」
「期待を大きく裏切られる」
という事態が起こります。(言い過ぎてごめんなさい)
この記事では、本当に信頼できる制作会社の見極め方と、絶対に発注してはいけない会社の特徴を解説します。
なぜ「理論は立派だが実現できない」制作会社が存在するのか
クライアント側に知識がないことを知っている
残酷な真実:
多くの企業は、Webやマーケティングの専門知識を持っていません。
だからこそ、制作会社に依頼するわけです。
しかし、この「知識がない」という状況を利用する制作会社が存在します。
彼らの手口:
- 専門用語を並べて煙に巻く
- 「UI/UXを最適化して、コンバージョン率を300%向上させます」
- 「最新のSEOアルゴリズムに完全対応したサイト設計です」
- 「AIを活用したパーソナライゼーションで、エンゲージメント率が劇的に向上します」
- 理論だけは立派に語る
- 実際にできるかどうかは関係なく、とにかく「凄そうなこと」を言う
- クライアントが「よく分からないけど、すごそう…!」と感心する
- 実現可能性は検証しない
- 「できます!」と言い切るが、実際にどうやって実現するかは考えていない
営業担当と制作担当が別人問題
悪質なケース:
- 営業担当:口がうまく、何でも「できます!」と言う
- 実際の制作担当:営業が約束したことを知らない、またはできない
結果: 発注後に「それはできません」「追加料金が必要です」と言われる。
理論が間違っていても気づかれない
恐ろしい事実:
クライアント側に知識がないと、制作会社の理論が間違っていても判定できません。
実例:
制作会社の営業トーク: 「とにかくページ数を増やせば、SEOに強くなります!」
真実: ページ数を増やすだけではSEOに強くなりません。質の低いページを大量に作ると、逆にGoogleからペナルティを受ける可能性があります。
しかし、クライアント側にSEOの知識がないと、「そうなんだ!じゃあ100ページ作ろう!」と信じてしまいます。
期待が大きい分、失望も大きい
最悪のシナリオ:
- 営業時:立派な理論を語られ、期待値が最高潮に
- 制作中:なかなか進まない、連絡が遅い
- 納品時:期待とまったく違うものが納品される
- 結果:期待が大きかった分、失望と不満が爆発する
この時、クライアントは気づきます。
「最初から実現できないことを、できると言っていたのか…」
発注してはいけない制作会社の3つの特徴
特徴1:すべて「できます!」と即答する
危険なフレーズ:
- 「それ、できますよ!簡単です!」
- 「どんなご要望にも対応できます!」
- 「当社ならすべて実現可能です!」
なぜ危険か?
本当にプロフェッショナルな制作会社なら、断言しません。
なぜなら、
- 実現可能性を検証する必要がある
- 技術的な制約を確認する必要がある
- 予算と期間が適切か判断する必要がある
即答する会社は、検証せずに「できます」と言っている可能性が高いです。
特徴2:デメリットやリスクを一切言わない
危険なパターン:
クライアント:「このデザインでお願いします」
危険な制作会社:「いいですね!最高です!すぐ制作します!」
信頼できる制作会社:「デザインは素敵ですが、このままだとスマホで見づらくなります。修正が必要ですが、よろしいですか?」
どんな制作にも、必ずデメリットやリスクがあります。
- この機能を実装すると、ページの表示速度が遅くなる
- このデザインは美しいが、使い勝手が悪い
- この予算では、希望の機能すべては実装できない
これらを一切言わない会社は、後で問題が起きます。
特徴3:専門用語ばかりで、分かりやすく説明しない
危険な会話例:
クライアント:「ホームページからの問い合わせを増やしたいです」
危険な制作会社:「では、UI/UXを最適化し、CTAボタンのマイクロコピーを改善、ヒートマップ分析でユーザビリティを向上させ、EFOを実装してCVRを最大化します!」
クライアント:「(よく分からないけど、すごそう…!)お願いします!」
優れた制作会社は、専門用語を使わず、分かりやすく説明できます。
信頼できる制作会社の説明: 「問い合わせを増やすには、3つのポイントがあります。1つ目は、お問い合わせボタンを目立たせること。2つ目は、入力フォームを簡単にすること。3つ目は、お客様の不安を解消する情報を載せること。これらを改善しましょう。」
この説明なら、クライアントも理解できます。
営業トークに騙されないための5つのチェックポイント
チェック1:「なぜそれができるのか」を聞く
質問例: 「コンバージョン率を300%向上させるとおっしゃいましたが、具体的にどのような方法で実現しますか?」
危険な回答: 「当社独自のノウハウがありますので、ご安心ください!」(具体的な説明がない)
信頼できる回答: 「まず現状のサイトを分析し、問題点を特定します。次に、お問い合わせフォームを改善し、入力項目を○個から△個に減らします。さらに…(具体的な説明が続く)」
チェック2:「デメリットは何か」を聞く
質問例: 「この提案にデメリットやリスクはありますか?」
危険な回答: 「デメリットはお金がかかるという点ですね。」
信頼できる回答: 「デメリットとしては、○○があります。また、△△のリスクもあります。ただし、これらは××という方法で対策できます。」
チェック3:「実績を具体的に」聞く
質問例: 「同じような業界での制作実績を教えてください」
危険な回答: 「実績は豊富です!」(具体例がない)
信頼できる回答: 「○○業界で、△△社のサイトを制作しました。その際、□□という課題があり、××という方法で解決しました。結果、問い合わせが◇◇%増えました。」
チェック4:「できないことは何か」を聞く
質問例: 「御社ができないこと、不得意なことを教えてください」
危険な回答: 「特にありません!何でもできます!」
信頼できる回答: 「当社は○○が得意ですが、△△は専門外です。もし△△が必要なら、信頼できるパートナー会社をご紹介します。」
チェック5:「担当者の経歴」を聞く
質問例: 「実際に制作を担当する方の経歴を教えてください」
危険な回答: 「ベテランのスタッフが担当しますので、ご安心ください!」(具体的な情報がない)
信頼できる回答: 「担当は○○で、経験年数は△年です。これまで□□業界の案件を◇件担当しており、××が得意です。」
信頼できる制作会社の見分け方
信頼できる会社の特徴1:「それは難しいです」と正直に言う
実例:
クライアント:「予算30万円で、ECサイトを作りたいです」
信頼できる制作会社:「正直に申し上げますと、本格的なECサイトを30万円で作るのは難しいです。その予算だと、機能を大幅に絞るか、無料のプラットフォーム(BASE、STORESなど)を使う方法をおすすめします。もしくは、予算を○○万円まで増やしていただければ、希望に近いものが作れます。」
この正直さが、信頼の証です。
信頼できる会社の特徴2:デメリットも伝える
実例:
クライアント:「とにかくデザインにこだわったサイトにしたいです!」
信頼できる制作会社:「デザインにこだわるのは素晴らしいです。ただし、注意点があります。デザイン重視にすると、ページの表示速度が遅くなる可能性があります。また、更新作業が複雑になることもあります。それでもデザイン優先でよろしいですか?それとも、デザインと使いやすさのバランスを取りますか?」
メリットだけでなく、デメリットも伝える。これが誠実な対応です。
信頼できる会社の特徴3:質問を返してくる
実例:
クライアント:「ホームページを作りたいです」
信頼できる制作会社:「ありがとうございます。まず、いくつか質問させてください。ホームページの目的は何ですか?誰に見てもらいたいですか?どんな行動を起こしてほしいですか?予算と納期の希望はありますか?」
なぜ質問するのか?
本当に良いものを作るには、クライアントの状況を深く理解する必要があるからです。
即答する会社は、理解せずに作り始めるため、期待外れになります。
信頼できる会社の特徴4:「やめた方がいい」と提案する
実例:
クライアント:「競合がやってるから、うちもアプリを作りたい」
信頼できる制作会社:「ちょっと待ってください。本当にアプリが必要ですか?アプリは開発コストが高く、継続的なメンテナンスも必要です。御社の場合、まずWebサイトを改善した方が、費用対効果が高いと思います。アプリはその後、必要になってから検討しませんか?」
クライアントの利益を最優先に考える。これが本物のプロです。
信頼できる会社の特徴5:過程を見せる
実例:
信頼できる制作会社の進め方:
- ヒアリング:「まず御社の状況を詳しく教えてください」
- 分析:「現状のサイトを分析しました。問題点は3つあります」
- 提案:「これらを改善するために、○○と△△を提案します」
- 理由の説明:「なぜこの提案なのか、理由を説明します」
- デメリットも伝える:「ただし、このデメリットがあります」
- 代替案の提示:「もし予算が厳しければ、こちらの方法もあります」
過程が見えるから、信頼できます。
「できません」と言える制作会社を選ぶべき理由
「できない」と言うのは勇気がいる
営業の本音:
「『できません』と言ったら、受注できないかもしれない…」
だから、多くの営業は**「できます!」と言ってしまいます**。
しかし、本当にクライアントのことを考えている会社は、「できません」と正直に言います。
「できない」と言える会社が信頼できる理由
理由1:誠実だから
嘘をついて受注するのではなく、正直に伝える。
理由2:専門性が高いから
何ができて、何ができないかを正確に判断できる。
理由3:クライアントの利益を優先しているから
無理して受注して、後で問題が起きるより、最初から断る方がクライアントのため。
依存を生む制作会社は最も危険
依存とは何か?
依存の定義:
クライアントが自分では何もできない状態にされること。
具体例:
- サーバーやドメインの契約を制作会社が代行し、クライアントは何も知らない
- 管理画面のログイン情報を教えてもらえない
- ちょっとした修正でも、毎回制作会社に依頼しないといけない
- FTP情報やサーバー情報を教えてもらえない
なぜ依存させるのか?
制作会社の本音:
「クライアントが自分で何もできない状態にしておけば、ずっとうちに依頼してくれる。継続的に収益が上がる。」
つまり、意図的に依存させているケースがあります。
失敗しない制作会社選び7つの質問
契約前に、必ずこれらの質問をしてください。
質問1:「御社ができないこと、不得意なことを教えてください」
期待する回答: 具体的に得意分野と不得意分野を説明してくれる。
危険な回答: 「特にありません。何でもできます!」
質問2:「この提案のデメリットやリスクを教えてください」
期待する回答: デメリットを正直に伝え、対策も提案してくれる。
危険な回答: 「特にデメリットはありません!」
質問3:「サーバーとドメインの契約は、どちらの名義にしますか?」
期待する回答: 「お客様名義で契約していただくことをおすすめします。代行も可能ですが、最終的にはお客様が管理された方が安全です。」
危険な回答: 「当社が代行しますので、お任せください!」
質問4:「管理画面やFTP情報は、共有していただけますか?」
期待する回答: 「もちろんです。すべての情報を共有します。」
危険な回答: 「セキュリティのため、当社のみで管理します。」(これは危険!)
質問5:「実際に制作を担当する方の経歴を教えてください」
期待する回答: 具体的な経歴、実績、得意分野を説明してくれる。
危険な回答: 「ベテランが担当します!」(具体的な情報がない)
質問6:「予算が足りない場合、正直に教えていただけますか?」
期待する回答: 「もちろんです。予算内で何ができるか、できないかを明確にします。」
危険な回答: 「予算内で何とかします!大丈夫です!」(後で追加請求される可能性)
質問7:「もし他の制作会社に変える場合、データはすべていただけますか?」
期待する回答: 「もちろんです。すべてのデータをお渡しします。」
危険な回答: 「それは契約違反になります」「データは当社の資産です」
理論よりも誠実さで選ぶ
【重要】制作会社選びの7つの鉄則
- 「できます!」と即答する会社は避ける → 本物のプロは、検証してから答える
- デメリットを伝えない会社は避ける → どんな提案にも、必ずデメリットがある
- 「できません」と正直に言う会社を選ぶ → 誠実さが、最も重要
- 専門用語ばかりの会社は避ける → 本当に優れた会社は、分かりやすく説明できる
- マイナス面も伝える会社を選ぶ → リスクを隠さないのが、プロの姿勢
- 依存させる会社は絶対に避ける → サーバー、ドメイン、ログイン情報はすべて自社管理
- 契約前に7つの質問をする → 曖昧な回答をする会社は危険
大阪でWeb集客会社選びをおこなうなら、失敗しないノウハウをこちらでご紹介しています。
立派な理論より、誠実な対応
制作会社を選ぶとき、多くの人は:
- 実績の数
- 料金の安さ
- 提案書の立派さ
- 営業トークの巧みさ
これらで判断してしまいます。
しかし、本当に重要なのは「誠実さ」です。
- できないことを「できません」と言える誠実さ
- デメリットも正直に伝える誠実さ
- クライアントを依存させない誠実さ
- 過度な期待を持たせない誠実さ
この誠実さがある会社を選べば、失敗しません。
逆に、どんなに立派な理論を語る会社でも、誠実さがなければ、必ず失敗します。
あなたの会社が、本当に信頼できるパートナーに出会えることを願っています。