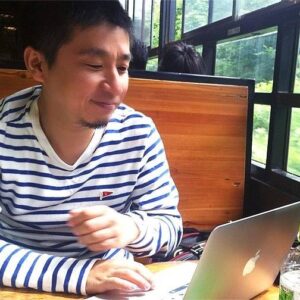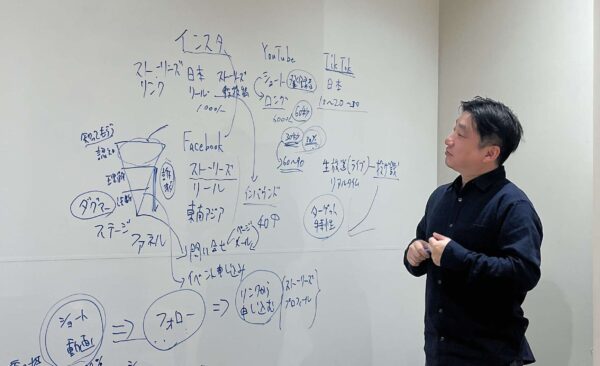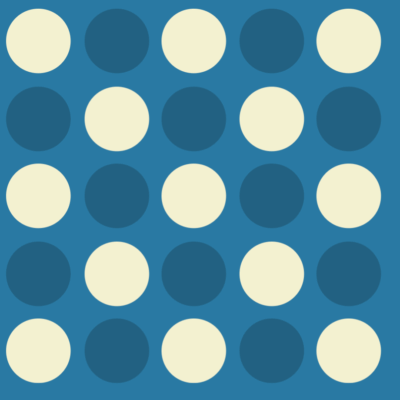
突然ですが、選択肢が多すぎて迷ってしまった経験、ありませんか?
スーパーでシャンプーを選ぶとき、
ネットで動画を探してるとき、
あれもこれも…と目移りして結局「やめとこ」ってなる、そんな経験。
実はこれ、
「脳の仕組み」に原因があります。
今回は、
「選択肢を減らすと売上が上がる」というマーケティングの裏側を、
できるだけ分かりやすくご紹介します!
「選択肢が多すぎると買われない」ってほんと?
人間の脳って、
4つくらいまでのものならパッと数えずに判断できるんですが、
それを超えると「数えるモード」に切り替わります。
この「瞬時に数がわかる仕組み」を
サビタイジング(Subitizing)と呼びます。
たとえば、
目の前に●●●があれば「3つだ!」と一瞬でわかるけど、
●●●●●●になった瞬間、「えーと…」と指折り数えたくなりますよね。
その「4つまでなら直感で選べる」
脳の性質を活かした設計を、マーケティングによく利用されます。
ゴロディロックス効果と4個ルール
サビタイジングと相性がいいのが、
「ゴロディロックス効果(Goldilocks Effect)」です。
これは、「多すぎず、少なすぎず、ちょうどいい選択肢がいちばん選ばれる」という考え方。
昔話『ゴルディロックスと三匹のくま』で、
熱すぎず冷たすぎず「ちょうどいいおかゆ」が一番好まれた、あれですね。
その「ちょうどよさ」が、
実は「4つくらい」なんですね。
だから選択肢は、
- 1〜4つに絞ると選ばれやすくなる
- 5つ以上になると、選ばれにくくなる
というわけです。
ジャム実験でも証明されています
有名な実験で、「24種類のジャムを並べたとき」と「6種類に絞ったとき」で売上を比較した実験があります。
なんと、6種類のほうが売上が10倍になったそうです。
理由はシンプル。
「選べないから買わなかった」。
ジャム実験については、
下の記事で詳しく説明しています。
↓↓↓
ジャム実験という選択的パラドックス・決定回避(選択回避)の法則を解説してみた
サビタイジング
「サビタイジング(Subitizing)」とは、
日本語では「瞬間的数認識」とも訳される現象です。
サビタイジングとは?
- 数を数えずに、瞬間的に数がわかる能力のこと。
- 通常、人は1〜4個程度の物体なら、一瞬で「いくつあるか」を正確に把握できます。
- 5個を超えると、正確に把握するには「数える」必要が出てきます。
たとえば、3つは分かる
目の前に●●●があったとき、
「3つだ!」とすぐ分かるのがサビタイジングです。
あらゆるところで応用されています
- 教育(算数・数概念の導入)
- デザイン(アイコンやメニューを少数に)
- マーケティング(選択肢を絞る)
つまり、
サビタイジングは「選択肢を増やしすぎると混乱する」現象を理解するうえでも、
とても重要な心理効果です。
人間の脳は、
4個までの物体は瞬時に「これくらいかな?」と直感で判断できますが、
5個以上になると判断が遅く誤認しやすくなるということが、
神経活動の観察により示されました
ネイチャーの論文より
↓↓↓
ニュース 2023年10月6日 脳は4つの物体の大きさを判断するのは簡単だが、5つになるとそうはいかない。その理由はここにある
ゴロテック効果とは?
「ゴロテック効果(Goleuix effect)」は、サビタイジングと密接に関わる心理現象で、選択肢を4つ以下に制限することで、消費者の決定プロセスが劇的に改善されるという効果です。これは、人間の瞬間的数認識能力(サビタイジング)の限界を活用したマーケティング手法として注目されています。
サビタイジングとゴロテック効果の相乗作用
サビタイジング(1-4個の瞬時認識)と
ゴロテック効果(4つ以下の選択肢最適化)は、
以下のように連携してマーケティング効果を高めます
認知負荷の軽減
人間の脳は4つまでの選択肢なら瞬時に全体を把握できるため、
比較検討にかかる認知的エネルギーが大幅に削減されます。
これにより「決定疲れ(Decision Fatigue)」を防ぎ、購買意欲を維持できます。
ヒックの法則との整合性
ヒックの法則によると、選択肢の数が増えるほど決定にかかる時間が対数的に増加します。
サビタイジングの限界(4個)内に選択肢を収めることで、決定時間を最小化できます。
神経科学的根拠
ヒックの法則を考慮すると、4つ以下の選択肢では決定時間が最短になり、ユーザーストレスが大幅に軽減されます。
最新の神経活動観察研究により、4個以下の物体を認識する際と5個以上を認識する際では、脳の活動パターンが明確に異なることが判明しています:
- 1-4個: 前頭前野の瞬間的活性化(直感的処理)
- 5個以上: 頭頂葉を含む複数領域の段階的処理(分析的処理)
この違いが、マーケティングにおける「4つルール」の科学的根拠となっています。
心理学的背景→なぜ4つが最適なのか?
マジカルナンバーとの関係
ジョージ・ミラーの「マジカルナンバー7±2」は短期記憶の限界を示していますが、
サビタイジング研究により、
瞬間的な処理能力はさらに限定的(1-4個)
であることが判明しました。この違いが重要です:
- 短期記憶容量: 7±2個(数えて覚える)
- 瞬間認識能力: 1-4個(直感で把握)
マーケティングでは
「考えさせる」のではなく「直感で選ばせる」ことが重要なため、
サビタイジングの限界である4個が最適となります。
選択回避の法則(ジャム理論)との統合
シーナ・アイエンガー教授のジャム実験では、24種類より6種類の方が購買率が10倍高いことが証明されました。さらに研究が進み、4つ以下では:
- 立ち寄り率: 高水準を維持
- 購買転換率: さらに向上
- 顧客満足度: 後悔が最小化
実践的マーケティング応用
選択肢が多すぎると逆効果になる。
この心理法則を実際のビジネスでどう使うか?ここでは、わたしが実際に活用してきたやり方をもとにご紹介します。
商品やサービスの選び方を「4つまで」にしぼる
たとえば、ホームページ制作のプラン。
「シンプルプラン」「集客プラン」「おまかせプラン」「まずは相談プラン」
このように4つまでにすると、選びやすさが格段に上がります。
実際に、プランを4つ以下に絞ったことで、お問い合わせ数が2倍になった例もあります。
カテゴリーも4つ+「その他」にする
ECサイトやホームページのメニューを10個以上並べていませんか?
実は、「4つ+その他」の構成にするだけで、クリック率がアップし、離脱も減ります。
たとえば:
- 商品カテゴリー:「美容」「健康」「生活」「趣味」+その他
- サービスカテゴリー:「SEO対策」「SNS運用」「ホームページ修正」「集客相談」+その他
これだけで、見やすさが変わります。
ECサイトでの応用例
商品カテゴリー分類:
- 従来:10以上のカテゴリー表示
- 改善:4つの主要カテゴリー+「その他」
- 結果:クリック率30%向上、直帰率20%減少
プラン選択画面: 松竹梅の3択に「お試し」を加えた4択構成により、各プランの特徴が瞬時に把握可能になります。
認知負荷を最小化するUI設計
ヒックの法則を考慮すると、4つ以下の選択肢では決定時間が最短になり、ユーザーストレスが大幅に軽減されます。
サビタイジング+ゴロテック効果の威力
サビタイジングとゴロテック効果を組み合わせることで:
- 瞬間的な認知処理により選択ストレスを排除
- 決定疲れを回避し購買意欲を維持
- 後悔の最小化により顧客満足度向上
- 転換率の最大化を実現
人間の生来持つ認知能力の限界を理解し、
それに合わせたマーケティング設計を行うことで、「選ばれやすい」環境を科学的に構築できるのです。
まとめ
選択肢を少なく見せるのもスキルのひとつ
人は「選択肢が多すぎると選べなくなる」もの。
それなら、最初から「4つくらい」に見せてあげるのが、やさしい設計です。
この設計の考え方、実は私がやってるホームページ制作や売れる設計にも活かしてます。