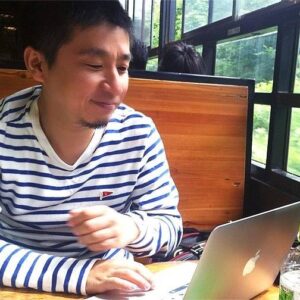ホームページで集客したいけれど、どうやったらいいか分からない。
そんな悩みを抱えていませんか?
今回は、実績の見せ方やLP(ランディングページ)の構成、
見出しの工夫など、改善ポイントを具体的にご紹介します!
実績の数は「6個以上」が目安
ホームページに掲載する「実績」、いくつくらいが最適か迷いますよね。
- 最低でも6個以上が理想
- 3〜5個だと“少ない”印象を与えることも
- ただし、目立つ大手企業や有名案件が1件あるなら、それを前面に出すのも効果的
実績の数が6個以上あるのが良いという理屈には理由があります。
人は、5以下の場合、
多いとは感じないという理論があるからです。
特に3つ以下の場合、
ものすごく分かりやすい数となります。
ジャム実験や、サビタイジングという法則、
そして松竹梅の法則とよばれるゴロテックス効果などですね。
これらで証明されています。
6個以上あると、「多い」と認識される
選択肢が多すぎると、逆に購入率が下がる。
これは「ジャム実験」で明らかになった心理現象です。
6種類の中から選ばせた方が、24種類よりも購入されやすく、
満足度も高まるという結果が出ています。
つまり、
ホームページの構成では
「選ばせすぎない設計」が重要です。
実績の数は、多いなと感じてもらうのが狙い
一方、
「実績」の見せ方は逆です。
実績は「多いな」と感じてもらうことで
信頼感が生まれるため、
ある程度の数が必要です。
人が一瞬で数を数えられなくなって、
「多い」と感じるのは6個以上から。
だから、
実績を掲載する場合は
最低でも6個以上を目安にするのがオススメです。
日本ではジャムの法則と呼ばれていますが、
コロンビア大学の心理学者アイエンガー教授がおこなった実験があります。
選択肢が多いと決断疲れを起こしてしまい、
決断しなくなるという法則です。
それが下のジャム実験です。
ジャムの実験とは?
「ジャム実験(アイエンガーとレッパーの研究)」とは、スーパーで試食のジャムを6種類と24種類で出したところ、選択肢が多い方が試食は増えたが、購入率は低下したという実験です。
つまり、選択肢が多すぎると迷って行動しなくなるという「選択のパラドックス」を示した有名な心理学研究です。
ほかにも、
どれくらいの数から多いと感じるのか?参考となる法則があります。
それが、下の2つ、
サビタイジングとゴロテックス効果です。
サビタイジング(Subitizing)とは?
ごく少数(通常1〜4個)の物の数を、
数えなくても瞬時に正確に把握できる能力のことを指します。
たとえば、サイコロを見た瞬間に「3」や「5」の目が分かるように、
目で見てすぐに「数を理解できる」直感的な数の認知です。
5個以上になると人はひとつずつ数える必要が出てきて、
サビタイジングではなく「カウント」に切り替わります。
マーケティングやデザインでも、
「3つだけ」「4つだけ」といった見せ方が効果的なのは
この心理が背景にあるからです。
ゴルディロックスの原理(Goldilocks principle)
ゴルディロックスの原理とは、
「多すぎず少なすぎず、ちょうどよいもの」が選ばれやすいという心理効果です。
たとえば、価格帯が3つあると多くの人は真ん中を選ぶ傾向があります。
選択肢設計に役立つ原理です。
日本では松竹梅の法則と呼ばれています。
サビタイジングとゴルディロックスの原理(松竹梅の法則)を解説する
実績の「質」を高めるには?行動経済学から考える信頼性のつくり方
ホームページに掲載する実績は「数」も大事ですが、より重要なのはその「質」です。
行動経済学では、「社会的証明」と「信頼性」が、購入や問い合わせの決断に大きな影響を与えるとされています。
たとえば、
- 有名企業との取引実績
- 業界内で話題になった成果
- 明確な数値で成果を証明できる事例
これらは、それだけで「すごそう」と思わせる社会的証明になります。
さらに信頼性を高めるポイントとしておすすめなのが、
- クライアント自身の顔出し写真
- 手書きのコメント
- 現場の様子を映した動画
- 社長や担当者が語るストーリー
といった「リアルな素材」の活用です。
たとえば、クライアントの社長が、
「このサービス、本当に助かったんです」と語ってくれる動画。
これだけで、
文字では伝わらない「熱量」や「信頼」が一気に高まります。
有名人や芸能人の使用例があれば、さらに強力ですし、
難しい場合は「◯◯のような方にも使われています」といった「共感できるストーリー」を添えるだけでも、グッと印象が良くなります。
実績は「見せ方」で何倍も価値が変わります。
ぜひ、印象に残る“質の高い実績”をホームページに取り入れてみてください。
見せ方と配置が信頼を左右する
よく「実績ページを作ったけれど、なかなか見てもらえない」という声を聞きます。
実はそれ、当たり前なんです。
多くの訪問者は、わざわざ実績ページまでたどり着きません。
さらに「お客様の声」や「インタビューページ」も、タイトルや導線に工夫がないと、ほとんどの人がスルーしてしまいます。
見られる実績にするためのコツ
ここでは実績を見られやすくするためのコツをいくつかご紹介します。
タイトルで興味を引く。
たとえば
「こんな悩みを解決した事例」や
「◯ヶ月で問い合わせが3倍になった方法」など、
読みたくなるタイトルが重要です。
序文で引き込む
「実はこのお客様、最初は全然うまくいってなかったんです…」というような、
続きが気になる冒頭にすることで、
読み進めてもらいやすくなります。
実績は分散して見せるのがベスト
実績は
トップページ・サービスページ・商品ページの途中に、
小さくてもいいので入れ込みましょう。
たとえば、
- サービス紹介の流れの中に「こんな結果が出ました」
- 商品の特徴を説明する横に「お客様の感想」
といった感じで、流れの中に自然に挿入するのがコツです。
実績ページは「まとめページ」として置いておくのはOKですが、それだけに頼るのはもったいない(読まれない)。
実績は「散りばめて見せる」という発想をぜひ取り入れてみてください。
具体的な見せ方事例
ここでは、具体的な見せ方を事例でご紹介します。
【事例1】整体院は「有名人と一緒に写った写真」で信頼度UP
個人整体院の事例。近所に住む元プロ野球選手が通っていたことがあり、
院内で撮ったツーショット写真を許可をもらって掲載。
「〇〇選手も信頼する施術」と見出しを入れたところ、
地域のファン層からの信頼を獲得し、月の問い合わせ数が増えた。
【事例2】不動産投資を教える塾で「お客様の声動画」を活用して成約率アップ
不動産投資を教える塾では、
生徒さんへインタビューした動画を撮影。
実際に塾で学んだ内容や投資実績などを話してもらった。
「めちゃくちゃ学びにつながった」
「塾に入って結果がこれだけ出た」という言葉が、
そのまま安心材料になり、入塾率が大幅に上昇。
【事例3】BtoB企業のサイトで「大手取引先のロゴ」を掲載
中小企業のBtoB企業が、
大手チェーンとの取引実績をトップページに掲載。
大手取引先のロゴとともに、その実績をトップページや目立つ場所に配置。
他の法人顧客からの信頼を得やすくなり、アポ率が改善。
【事例4】Web制作会社が「社長の想い動画+手書きメモ付き」で共感を呼ぶ
自社のトップページに「なぜこの仕事をしているのか」という社長メッセージを動画で掲載。
さらに、実際にお客様からもらった手書きのメモ(「本当に助かりました!」という感謝の言葉)も画像で掲載。
温かみと人柄が伝わり、「他と迷ったけど、ここにお願いしたいと思いました」という問い合わせが増加。
他にも下のようなテクニックがあります。
見出しだけで内容が分かるようにする
ユーザーは「飛ばし読み」をします。そのため、見出しの工夫はとても重要です。
- 「ご挨拶」「こんなことありませんか?」のような曖昧な見出しは避ける
- 見出しだけで内容が把握できるように
- 「相談しやすい弁護士事務所を目指しています」など、結論を最初に伝える
PREP法(結論→理由→具体例→まとめ)を使えば、文章にもメリハリが出て、読みやすくなります。
LP(ランディングページ)は商品ごとに最適化する
例えば「ひげ脱毛」などの具体的な商品がある場合、その商品のために専用LPを用意しましょう。
LP構成の基本
- タイトル(H1):キーワード+価格や強み(例:金沢の完全個室で髭脱毛5,000円〜)
- 課題提起:「こんなお悩みありませんか?」
- 解決策:当店の特長やサービス内容を紹介
- 実績や写真:具体的なビフォーアフターやお客様の声
- よくある質問(必要に応じて)
- お問い合わせボタンやバナー
バナーはページ途中と最後に2カ所設置するのがおすすめ。
ユーザーが読み進めて決断したタイミングを逃さないようにしましょう。
モバイルユーザーを意識した設計も大事
- スクロール量を減らす
- バナーは目立ちすぎず自然な位置に
- 追尾型バナー(スクロールに追従するもの)は業種によっては有効
ホームページでの集客を本気で改善したい方へ
実績の見せ方、見出しの構成、LPの設計などを見直すだけで、ホームページの反応は劇的に変わります。
「自分でやってみたけど、うまくいかない…」
「もっと具体的に教えてほしい!」
そんな方のために、ホームページ集客改善のマンツーマン講座もご用意しています。