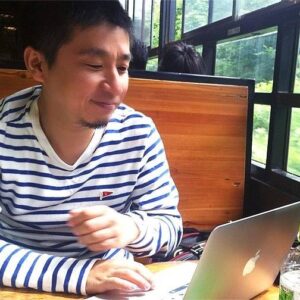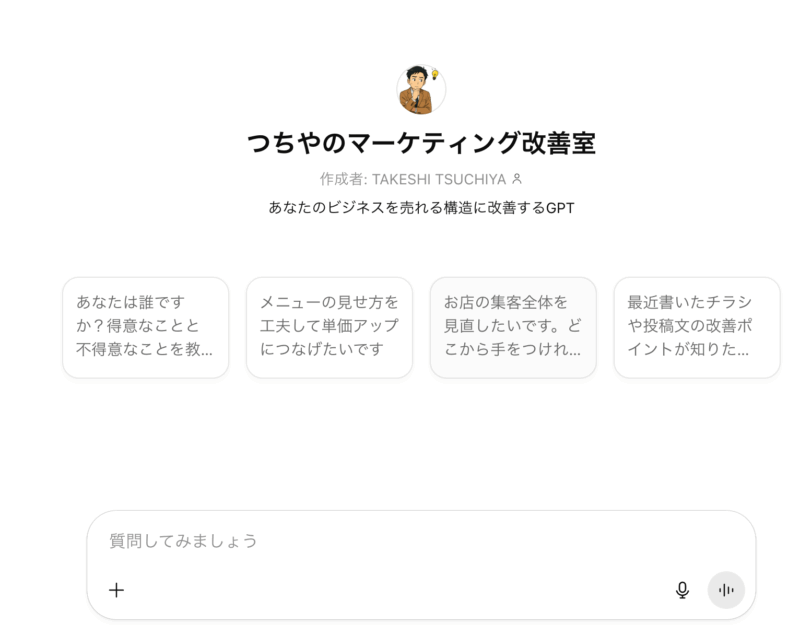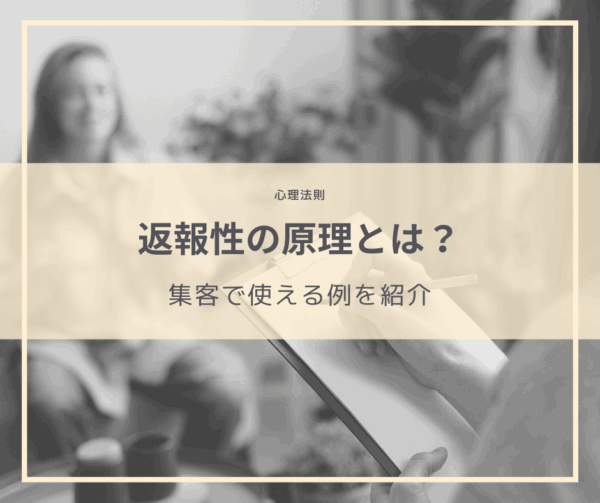「会社のブログで集客力を増やそう!」と考えた場合、社長の日常や会社の出来事を投稿しているだけの企業が驚くほど多いです。
しかし、企業サイトでの日記投稿は、集客力を大幅に下げるよくない行為です。
ブログでは専門的な記事をたくさん書くことで、集客力がアップします。コンテンツブログとも呼ばれているブログ記事です。
私が知ってる会社や事業者さんでは、日記コンテンツを専門的な記事に変更しただけで月間サイト訪問者が増加した事例がいくつもあります。
今回は、日記を企業ブログでは書いてはダメなのこと、その理由や対策などをまとめてみます。
日記ブログがSEOに悪影響を与える
かつてブログといえば、日記が主流でした。しかし、ブログの氾濫から日記というコンテンツでは差別性が困難となり、SEOに関しても悪影響を与えることが多くなってしまいました。
ここではそのことについて解説します。
1. サイト全体の専門性が薄くなってしまう
Googleは「このサイトは何の専門家なのか」を非常に重視しています。これはE-A-T(専門性・権威性・信頼性)の一部ですが、日記コンテンツが増えるほど、この評価が下がってしまいます。
食品を扱う会社での実際の失敗事例をお話しします。
社長が毎日の食事やゴルフへ行く様子を投稿し続けたところ、3ヶ月後には「食品」関連のキーワードで検索順位が数十位下落してしまいました。その結果、月間のサイト訪問者が減少するという事態になったのです。
2. 訪問者の期待と内容のミスマッチを招く
あなたの会社のサービスを探している人が、検索結果からサイトを訪問したとき、出てくるのが社長の趣味の話だったらどうでしょうか?
このミスマッチが原因で起こる問題は深刻です。
- 直帰率がはげしくなる(すぐにサイトから出て行く)
- 平均滞在時間が30秒未満になる
- Googleから「このサイトは役に立たない」と判断される可能性がある
結果的に検索順位がさらに下がるという悪循環に陥ってしまいます。
3. 重要なページが埋もれてしまう
日記記事が増えると、本当に大切な「サービス紹介」や「実績紹介」のページが見つけにくくなります。これにより、問い合わせにつながるページへの流入が減ってしまいます。Googleのクローラーも、どのページが重要なのか判断しにくくなり、サイト全体の評価が下がる原因となります。
4. 薄い内容のページが多いと評価が下がる可能性がある
Googleは最近、価値の低いコンテンツが多いサイトに対して厳しい評価を下すようになりました。日記のような個人的な内容は、ビジネスを探している人にとって価値が低いと判断される可能性があります。
5. キーワードの一貫性が失われる
日記コンテンツは、企業のメインキーワードとの関連性が低いため、サイト全体のキーワード戦略を混乱させます。
例えば、税理士事務所のサイトに「今日のランチ」「週末の趣味」といった記事があると、Googleは「このサイトは税務の専門サイトなのか、それとも個人ブログなのか」を判断できなくなってしまいます。
この結果、「税理士 大阪」「確定申告 相談」といった重要なキーワードでの検索順位が上がりにくくなり、本来獲得できるはずの見込み客を逃してしまうのです。
日記コンテンツの適切な移行方法
ここでは日記コンテンツをどうやって移行するか、その方法についてご紹介します。
ステップ1: 既存の日記記事を整理する
まず、現在ある日記記事を大きく3つに分けてください。
削除対象
- 完全に個人的な内容(食事、趣味、家族の話など)
- 企業活動と全く関係のない投稿
移行対象
- 会社の雰囲気を伝える価値のある内容
- ブランドの人間性を示す投稿
- 社長やスタッフの人間性を表す投稿
リライト対象
- 専門性を加えることで価値を高められる内容
- 業界知識と関連付けられる投稿
移行先としては、noteが長めの記事に適しており、Instagramは写真中心の投稿に向いています。個人の日記に近いコンテンツはFacebookが向いているでしょう。ほんとの日記はアメブロも向いています。
ステップ2: 専門性を保ちながら親しみやすさを演出
「日記をやめたら堅い会社だと思われるのでは?」という心配は不要です。
推奨するアプローチ
- 「お客様からこんな質問をよくいただきます」
- 「現場での体験から学んだこと」
- 「業界の動向について思うこと」
- 「よくある誤解について解説します」
避けるべき内容
- 今日の昼食メニューの紹介
- 週末の家族との過ごし方
- 読んだ本の個人的感想
- 天気や季節の挨拶のみの投稿
これらは企業サイトでは価値を提供しません。SNSや外部のブログサービス(アメブロなど)の利用を検討しましょう。
ステップ3: コンテンツのネタを継続的に見つける方法
記事のネタに困ることはありません。以下の方法を活用してください。
お客様の声を活用
- 営業担当者から「今月多かった質問」を聞く
- 電話やメールでの問い合わせ内容をメモ
- アフターサービスで出てくる疑問点を記事化
業界情報の活用
- 法改正や制度変更の解説
- 新技術や新サービスについての見解
- 業界の課題と解決策の提案
AIツールの活用
ChatGPTなどを使って「〇〇業界でお客様が困っていることを10個教えて」と質問するだけで、記事のテーマが次々と出てきます。
【SEO強化】専門記事で検索上位を狙う具体的な方法
ここでは、SEOを強くする専門性の高い記事を書いて、上位表示を狙う方法をご紹介します。
キーワード戦略の立て方
専門記事でSEO効果を最大化するには、適切なキーワード戦略が欠かせません。まず、あなたの業界でお客様が実際に検索するキーワードをリストアップしてください。
例えば税理士事務所なら以下のようなキーワードが考えられます。
- 「確定申告 やり方」
- 「節税対策 中小企業」
- 「法人税 計算方法」
- 「経費 範囲」
- 「税務調査 対応」
重要なのは、1つの記事で1つのメインキーワードに集中することです。
「確定申告」について書くなら、その記事は確定申告に関する情報だけに特化し、他のトピックは別の記事で扱うようにしましょう。
記事タイトルの最適化テクニック
記事タイトルは検索結果で最初に目に入る部分なので、非常に重要です。効果的なタイトルを作るポイントは以下の通りです。
タイトル作成のコツ
- メインキーワードを必ず含める
- 数字を使って具体性を出す(「5つのステップ」など)
- 年度を明記する(「2024年版」など)
- 読者の願望に訴える言葉を使う(「楽にする」「失敗しない」など)
「確定申告の準備方法」よりも「【2024年版】確定申告の準備を楽にする5つのステップ」の方が、具体性があり、読者の関心を引きやすくなります。
内部リンクで記事同士をつなげる
専門記事を書いたら、関連する他の記事と内部リンクでつなげることが重要です。これにより、読者は関連情報を簡単に見つけることができ、サイト内での滞在時間も長くなります。
例えば、「確定申告の準備方法」の記事を書いたら、以下のような関連記事へのリンクを設置します。
- 「経費計算の基本ルール」
- 「領収書の整理方法」
- 「青色申告のメリット」
これにより、Googleはあなたのサイトが税務について体系的な情報を提供していると認識し、検索順位の向上につながります。
【重要】更新頻度は維持する
日記をやめても、更新頻度を下げてはいけません。Googleは新鮮な情報を評価するため、定期的な更新は必須です。
更新を止めた場合に起こる問題
- サイトが「古い情報しかない」と判断される
- 検索結果での表示順位が下がる
- 競合他社に追い抜かれる
実際に、ビジネス関連のサイトが3ヶ月更新をストップした結果、サイト訪問者が60%も減り、元に戻すのに半年以上かかった事例があります。
効率的な更新スケジュールの例
- 月曜日:お客様からの質問を元にした記事
- 水曜日:業界ニュースについての解説
- 金曜日:サービス・商品の詳しい紹介
読者に価値を提供する記事の作り方
ここでは、価値を提供する記事を作り方をまとめてみます。
ターゲット読者の明確化
効果的な専門記事を書くには、まず「誰に向けて書くのか」を明確にする必要があります。
ペルソナ設定の例(税理士事務所の場合)
- 年齢:40代〜50代
- 職業:中小企業の経営者
- 従業員数:10名程度
- 課題:税務処理が複雑で時間がかかる
- ITスキル:あまり詳しくない
- 求める情報:効率化の方法、費用の目安
このように具体的なペルソナを設定することで、その人に響く内容を書くことができます。
読者の検索意図を理解する
読者がそのキーワードで検索する理由を深く考えてみてください。
検索意図の例
- 「確定申告 やり方」→基本的な手順を知りたい
- 「節税対策」→具体的に税金を減らす方法を求めている
- 「税務調査 対応」→実際に調査が入った時の対処法を知りたい
この検索意図を正確に理解し、それに応える内容を提供することで、読者の満足度が高まり、検索順位も上がりやすくなります。
競合記事を分析して差別化を図る
あなたが狙うキーワードで実際に検索して、上位に表示される記事を確認してください。それらの記事と差別化するポイントは以下の通りです。
差別化の方法
- より詳しい解説を提供する
- 実際の体験談や事例を加える
- 最新の情報やデータを含める
- 独自の視点や切り口を提示する
- より分かりやすい図表や画像を使用する
専門性の高い記事の書き方
専門性の高い記事を書く方法をご紹介します。
記事構成の基本パターン
効果的な記事構成は「問題提起→共感→解決策→具体例→行動喚起」の流れです。
記事構成の例
- 問題提起 「確定申告の準備で毎年困っていませんか?」
- 共感 「多くの経営者の方が同じ悩みを抱えています」
- 解決策 「実は効率的な準備方法があります」
- 具体例 「実際の事例をご紹介します」
- 行動喚起 「まずは領収書の整理から始めてみてください」
専門用語の適切な使い方
専門用語を使う際は、必ず分かりやすい説明を加えてください。
悪い例
「減価償却の定額法と定率法を比較検討し、ROIを最大化する必要があります」
良い例
「設備投資をした時の経費処理には『減価償却』という仕組みがあります。これは高額な設備を購入した時に、その費用を数年に分けて計上する方法です」
一般の人でも理解できるよう工夫することが大切です。
【技術的SEO】サイト全体を最適化する方法
ページの表示速度を改善する
Googleは表示速度の速いサイトを評価します。改善方法は以下の通りです。
表示速度改善のポイント
- 画像のサイズを最適化する
- 不要なプラグインを削除する
- キャッシュ機能を活用する
特にスマートフォンでの表示速度は重要です。モバイル端末での表示速度が遅いと、検索順位に大きく影響するため、定期的にPageSpeed Insightsなどのツールでチェックしてください。
サイト構造を整理する
サイト全体の構造が整理されていると、Googleのクローラーがページを理解しやすくなります。
構造改善のポイント
- カテゴリーを明確に分ける
- パンくずリストを設置する
- サイトマップを作成する
- URLを分かりやすい構造にする
SSL化とモバイル対応を確実に
HTTPSでのSSL化は現在必須の対応です。また、モバイルファーストインデックスにより、スマートフォンでの表示がSEOに大きく影響するため、レスポンシブデザインでの対応を確実に行ってください。
改善効果をチェックする方法
確認すべき数値
改善効果を測定するために、毎月チェックしたい指標は以下の通りです。
主要指標
- サイト訪問者数の推移
- 問い合わせ件数の変化
- 検索結果での表示順位
- 滞在時間の改善
- 直帰率の変化
- コンバージョン率
これらの数値が向上していれば、専門性重視の記事戦略が成功していることを示しています。
使いやすい無料ツール
Googleアナリティクス
- サイト訪問者数と行動パターンが分かる
- どの記事が読まれているか把握できる
- 問い合わせにつながる記事を特定できる
Googleサーチコンソール
- 検索キーワードと順位が分かる
- どの記事が検索結果に表示されているか確認できる
- サイトの技術的な問題を発見できる
どちらも無料で使える優秀なツールです。
競合他社との比較分析
定期的に競合他社のサイトをチェックし、以下の点を確認してください:
チェックポイント
- どのようなコンテンツを発信しているか
- どのキーワードで上位表示されているか
- 更新頻度はどの程度か
- どのような記事構成になっているか
これにより、自社の強みを活かせる分野や、改善すべきポイントが見えてきます。
【長期戦略】継続的な成果を生む仕組み作り
コンテンツカレンダーの作成
継続的に質の高い記事を公開するために、3ヶ月先までのコンテンツカレンダーを作成しましょう。
カレンダーに含める要素
- 季節性のあるトピック
- 業界イベントに合わせた記事
- 定期的に更新が必要な情報
- お客様からの質問が多い時期に合わせた記事
計画的に配置することで、効率的な運営が可能になります。
社内体制の整備
記事作成を継続するために、社内の体制を整えることも重要です。
体制整備のポイント
- 誰が記事を書くのかを明確にする
- 誰が校正するのかを決める
- いつ公開するのかを決める
- 営業チームからの情報収集システムを作る
- お客様の声の共有システムを構築する
記事の定期的なリライト
一度公開した記事も、情報の更新や追加により、さらに価値を高めることができます。
リライトのタイミング
- 法改正や業界の変化があった時
- 新しい事例や統計データが入手できた時
- 検索順位が下がってきた時
- より詳しい情報を提供できるようになった時
これにより、検索順位の維持・向上が期待できます。
【失敗を防ぐ】よくある間違いと対策
間違い1: 専門的すぎて読者が理解できない
専門用語ばかりで、お客様が読んでも理解できない記事になってしまうケースがあります。
対策
- 専門用語には必ず説明を付ける
- 具体例を多く使う
- 「中学生でも分かる」レベルを目指す
- 図表や画像を使って視覚的に説明する
間違い2: 毎日更新にこだわって質が下がる
更新することが目的になって、内容の薄い記事を量産してしまう失敗もよく見られます。
対策
- 「毎日」よりも「質の高い内容」を重視する
- 週1〜2回の更新でも十分
- 1記事最低3,000文字以上を目安にする
- しっかりとリサーチする時間を確保する
間違い3: SEOを意識しすぎて不自然になる
検索キーワードを無理に詰め込んで、読みにくい文章になってしまうこともあります。
対策
- まず読者のことを考えて書く
- キーワードは自然に使う
- 書いた後で声に出して読んでみる
- 第三者に読んでもらって感想を聞く
間違い4: 競合の真似だけで独自性がない
競合他社の記事を参考にすることは重要ですが、そのまま真似するだけでは差別化できません。
対策
- あなたの会社ならではの視点を含める
- 実際の体験談を追加する
- 独自のノウハウを提供する
- より詳しい情報や最新のデータを加える
まとめ
この記事を読んでいるあなたは、きっと本気で集客を改善したいと考えているはずです。
今、あなたの前には2つの道があります。1つは、このまま日記を続けて競合に負け続け、問い合わせが増えず、「なぜ効果が出ないのか」と悩み続ける道です。
もう1つは、今すぐ専門家としての発信に切り替えて競合を大きく引き離し、問い合わせが着実に増え、業界での信頼と地位を築く道です。
日記で集客できる時代は完全に終わりました。専門性の高い情報発信だけが、持続的な成果をもたらします。
この記事を最後まで読んだあなたなら、必ず変化を起こせます。今すぐ行動を始めましょう。