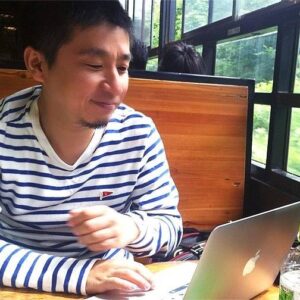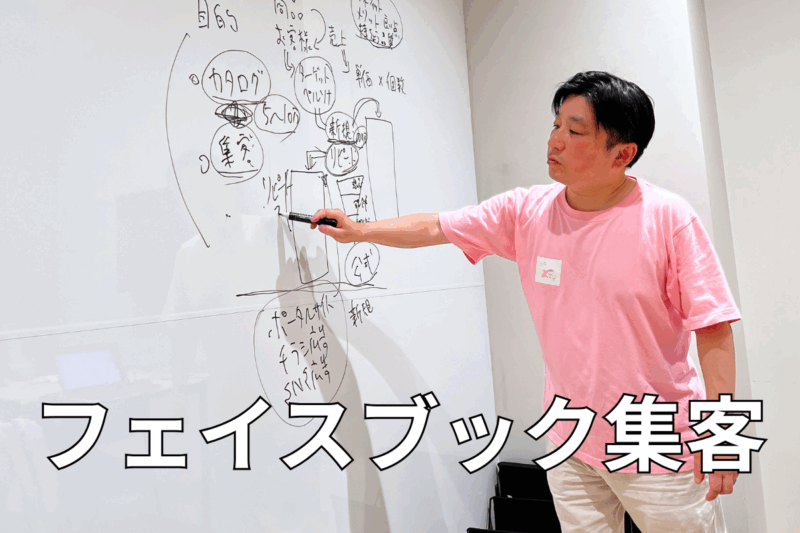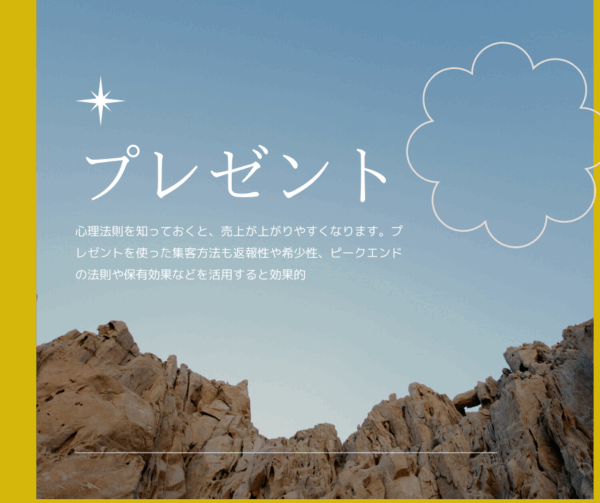中小企業で「利益が残らない…」という悩み、よく聞きます。
これは、売上の問題ではなくて
「粗利率」が低すぎる ことが原因だったりします。
今回は、売上を上げるよりも早くて効果的な
「粗利を劇的に上げる方法」についてお話します。
そもそも粗利とは?
まず、ざっくり定義をおさらいします。
- 粗利(売上総利益)= 売上 - 原価
要は、モノやサービスを売ったときに「どれだけ利益が残るか」です。
飲食店なら、料理を出していくら儲かるか。
整体院なら、施術をしていくら残るか。
この「粗利」が低いと、どれだけ売れても、人件費や家賃で全部消えるわけです。
【方法1】値上げできる商品を作る
中小企業は、「売れる商品」よりも「儲かる商品」を持ってるかが超重要です。
儲かってない企業は、「売れてるけど全然利益が出ない商品」が主力になっているケースが多いです。
そこで、
値上げしても喜ばれる商品
手間がかからず利益率が高い商品
をセットで考えるようにしています。
たとえば、
- 原価1,000円 → 売値2,000円(粗利50%)の商品より
- 原価500円 → 売値1,800円(粗利72%)のほうが、儲かりますよね。
【方法2】原価をちゃんと把握する
意外と「原価を正確に把握してない」社長さん、多いです。「なんとなくこのくらいかな〜」ってやってると、粗利計算がぐちゃぐちゃになります。
細かい仕入れや人件費、外注費、広告費・・・
ひとつひとつ丁寧に見直すだけで、「あれ、めちゃくちゃ無駄があるぞ?」って気づけます。
【方法3】セット商品・定額サービスにする
バラ売りよりも、セット販売・定額制・サブスクにするだけで粗利は上がります。
たとえば、
1回1,000円の商品をバラで売るよりも
月3,000円で「使い放題」にしたほうが、お客さんの利用単価は上がります。
これは、ホームページ制作も同じです。
1ページ1万円より、
「10万円で、LP+SNS+SEOを全部やります」のほうが、お客さんにとっても分かりやすく、提案も通りやすいですよね。
結果的に、利益率も上がります。
【方法4】「人を減らさず、無駄を減らす」
粗利改善といえば「人件費削減」って言われがちですが、
人を減らす前に、無駄な作業を減らすのが鉄則です。
- 2回やってることを1回にまとめる
- お客さんとのやりとりをテンプレート化する
- AIで、初回案内・説明・文書づくりを自動化する
これだけで、スタッフの時間が空いて、少人数で回せる体制が作れます。
実際、AIを使いはじめると、
「外注しないとムリ」と思ってた仕事が、ほとんど自分で回せるようになる人がほとんどです。
【方法5】「全部自分でやらない」選択肢を持つ
粗利の改善を本気で考えるなら、「やらない勇気」も必要です。
- 利益率が低いけど、忙しい仕事
- 頼まれて断れずやってる仕事
- 安すぎて人に任せられない仕事
これらは、ぜんぶ「時間と体力のムダ食い」です。
「やらない」「誰かに任せる」「もっと粗利が出ることに集中する」
という選択肢を持ちましょう。
これは、精神的にもラクになります。
粗利アップを阻む「思い込み」3選
粗利を改善しようとすると、必ずぶつかる「壁」があります。
それが——
経営者や現場の中にある「思い込み」です。
意外にも、この思い込みがブレーキになって、
利益アップのチャンスを自ら潰してしまってるケースは、めちゃくちゃ多いです。
今回は、特に多い3つの思い込みを取り上げて、
「どう考えたらいいか?」「どう対策すればいいか?」を解説していきます。
思い込み1
「値上げしたら顧客が離れる」
これ、一番よく聞きます。ある意味、事実だからです。
たとえば、5,000円のサービスを7,000円にしたら、
「今までの顧客が離れるんじゃないか」
「新規が来なくなるんじゃないか」
と不安になりますよね。
▼でも実際はどうか?
多くの顧客は、値段よりも納得感や信頼感で選んでいます。
実際、わたしの回りでも、
料金を1割〜2割上げたにも関わらず、売上は全く下がらなかった例はたくさんあります。
なぜかというと、
値上げした分、サービスの質や対応を良くしてからですね。
【対策】値上げの前に「伝え方」を工夫しよう
- なぜ値上げするのか(原価上昇、品質維持のためなど)
- どういう価値が上がるのか(対応、品質、アフターサポートなど)
- いつから、どのくらいの価格になるか
こうしたことを、事前にきちんと伝えるだけで、納得してくれるお客様は多いです。また常連客さんには、必ず価値を上げることをやっていきましょう。
思い込み2
「原価を削ると、品質が落ちる」
これも、根強い思い込みの一つです。
「安く仕入れたら、品質が悪くなるんじゃないか」
「経費を削ったら、サービスのレベルが下がるんじゃないか」
っていうやつですね。
▼でも実際はどうか?
粗利を上げている会社ほど、「ムダな原価を見直す努力」をしています。
それは決して「安物を仕入れろ」って意味ではなく、
- 無駄な梱包資材を減らす
- 在庫を抱えすぎないようにする
- 一部作業をAIやツールに切り替える
- 高すぎる外注先を見直す
など、品質に影響しない部分から改善していきます。
【対策】こだわりコストとムダコストを分けて考える
まずムダはないか見ていきます。
- 品質や満足度に直結するコスト → できるだけ残す
- お客さんが気づかない余計なコスト → 真っ先に削る
この整理をすると、「あ、ここいらなかった」というコストが結構出てきます。
思い込み3
「競合が安いから、ウチは価格を上げられない」
「隣の会社が3,000円だから、うちは2,800円じゃないと…」と考える経営者さん、めっちゃ多いです。
▼現実は?
安さで選ばれる商品は、結局どんどん価格が下がっていきます。
その中で戦うのは、体力のある大手だけです。
個人事業や中小企業は、
価格以外の魅力で勝負すべきです。
たとえば、
- 親身な対応(「あなただからお願いしたい」と言われる)
- アフターフォローが手厚い(問い合わせ対応、サポートが安心)
- 地元密着で安心感がある(遠方に依頼するより安心)
- 自社だけのノウハウ・強みがある
など、価格以外の価値を伝えられると「高くても選ばれる」ようになります。
【対策】「値段」じゃなく「価値」を伝えよう
- 他社より高い理由を、しっかり言語化する
- お客さんの声(口コミ、事例)を前面に出す
- ストーリーや背景(こだわり、創業の想い)を丁寧に伝える
これだけでも、「ここにお願いしたい」という指名につながります。
粗利の改善は「継続的な取り組み」が成功の鍵
粗利の改善は一度やって終わりではありません。市場環境の変化に応じて、継続的に見直していく必要があります。
成功するための3つのポイント
- 数字に基づいた判断:感覚ではなく、データで施策を決定
- 段階的な実行:いきなり大きく変えず、小さくテストしながら拡大
- 全社一丸の取り組み:営業・製造・管理部門の連携が不可欠
まずは自社の現状把握から始めて、できることから一つずつ実行していきましょう。小さな改善の積み重ねが、必ず大きな成果につながります。