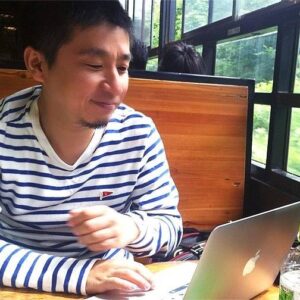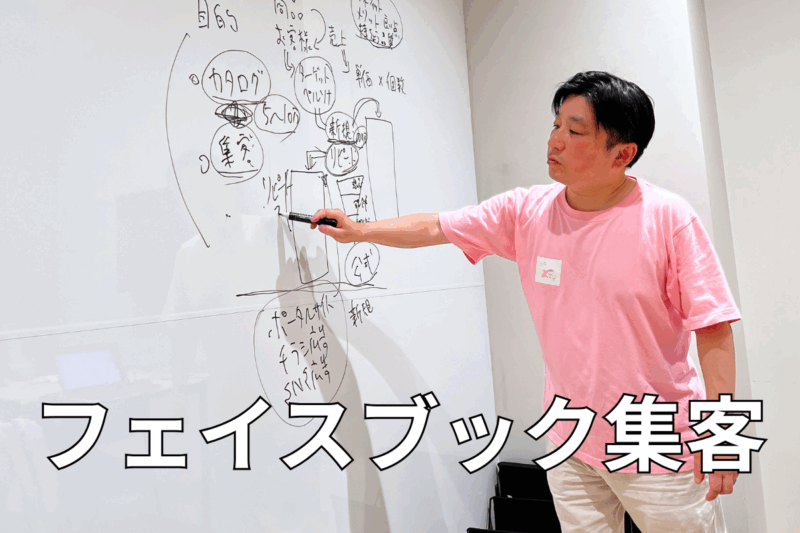「選べることは、いいことだ」と思っていませんか?
実は、選択肢が多すぎると、逆に「選べなくなる」ことがあります。
これは「選択のパラドックス」とも呼ばれ、
マーケティングの世界でもとても重要な理論です。
今回は、その代表例として知られる「ジャム実験(アイエンガーとレパーによる研究)」をもとに、
「なぜ選択肢が多いと人は動けなくなるのか?」という心理のしくみを、
できるだけわかりやすく解説してみました。
ホームページ設計や商品ラインナップの見せ方に、
すぐに応用できる内容です。
ぜひ最後までご覧ください。
ジャム実験(Jam Experiment)とは?
心理学者のシーナ・アイエンガー(Sheena Iyengar)と
マーク・レパー(Mark Lepper)がおこなった有名な実験です。
1. 実験の目的と背景
心理学者Sheena Iyengar(コロンビア大)とMark Lepper(スタンフォード大)は、
「選択肢が多すぎると消費者の購買意欲が下がるのでは?」という仮説を検証するため、
食品店でジャムの試食販売実験を行いました。
2. 実験デザイン
- 限定選択条件:6種類のジャムを展示
- 過剰選択条件:24種類のジャムを展示
来店者がどちらのテーブルに足を止め、何を購入するかを比較。
3. 主な結果
- 興味を引いたのは24種の方 → 約60%が立ち寄ったのに対し、6種展示は約40%
- 購入率は逆転 → 6種のテーブルでは購入率が約10倍高くなった
- 満足度も高い → 選択肢が少ないほど、消費者の満足感や後悔の少なさが確認された
この結果から、
「選択肢が多すぎると、逆に人は選べなくなる(決定回避)」という現象が確認されました。
マーケティングや商品設計、
ホームページの構成において「選択肢の数」はとても重要なポイントだとされ、
この実験は「選択のパラドックス」の象徴的な例として広く知られています。
要約表
こちらが「ジャムの法則」の要点をまとめた要約表です。
選択肢が多すぎると、かえって人は決断できなくなる。
そんな心理現象を端的に示したのが「ジャム実験」と呼ばれる有名な研究です。
「選択肢が多い=親切」と思いがちな方こそ、
一度立ち止まって見直すヒントになるかもしれません。
| 条件 | 来訪者数 | 購入率 | 満足度 |
|---|---|---|---|
| 少数選択(6種程度) | やや少ない | 高い (約10倍) | 高い |
| 多数選択(24種) | 高い | 低い | 低い |
この研究は、いわゆる「選択の逆説(Paradox of Choice)」を裏付け、
たくさん選べることが必ずしも良い結果につながらないことを示しています。
LP・トップページ・商品構成を考える際にも「迷わず選べる環境づくり」が重要です。
なぜ選択が多すぎると逆効果なのか?
選択肢が多すぎると逆効果になる理由は、主に以下の3つです。
選択の複雑さが心理的負担に
選択肢が増えると比較対象も増え、評価に時間と集中が必要。ただし認知リソースには限界があり、結果として意思決定が混乱する。
選択疲れによる購買意欲の低下
決断の重みや責任感から、選ぶ行為自体にストレスを感じるようになる。最終的に購入をためらいがちになる。
後悔や不満の増大
選択肢が多いほど、選ばなかった他の選択肢への未練が生まれる「後悔」が強くなり、満足度は下がる傾向に。
マーケティングやウェブ制作での示唆
マーケティングやウェブ制作における「選択肢が多すぎると逆効果」という
知見から得られる示唆は、次のようなものがあります。
ホームページのメニューや導線は「シンプル」に
ナビゲーションやボタンが多すぎると、
訪問者が「どこをクリックすればいいのか分からない」と迷い、
離脱の原因になります。
重要な導線だけに絞ることが大切です。
選択肢を減らすだけで効果的
製品バリエーションが豊富でも、
LPやトップページでは6〜10程度の厳選した選択肢を提示することで、
コンバージョンが向上しやすくなります。
プランが10個あるよりも、松・竹・梅の3つ構成のほうが比較しやすく、選びやすい。
これは「ゴルディロックスの原理(ちょうどいい効果)」とも関連します。
おすすめの提示で「選択支援」を
すべてを平等に並べるよりも、
「人気No.1」や「はじめての方におすすめ」など、
判断のヒントを与えることで、選択ストレスを減らせます。
ニーズが明確なら多少多くてもOK
消費者に強い好みや明確な目的がある場合は、
多くの選択肢がむしろ比較手段となり、有効になります。
実績や事例も「選ばせすぎない」
「実績100件!」と並べるよりも、代表的な6件を丁寧に見せた方が信頼感が増します。
さらに具体的なストーリーやビジュアルがあれば、なお効果的です。
比較しづらい商品は特に注意
違いが分かりにくい商品や初心者向けジャンルでは、
選択肢を絞って「代表例」+「比較ポイント」で提示するのが効果的。
使用事例
「ジャムの法則(選択肢が多すぎると購買意欲が下がる現象)」は、
実際のビジネスや日常の場面で幅広く使われています。
以下にいくつかの具体的な事例と、なぜこの法則が有効に働くのかをくわしく解説します。
サブスクリプションの料金プラン(例:動画配信サービスや学習アプリ)
状況:
多くの企業は、料金プランを「ベーシック・スタンダード・プレミアム」のように3つに絞っています。
理由:
プランが多すぎると、ユーザーは「自分にとって最適なプランはどれだろう…」と悩み、結局申し込みをやめてしまうケースがあるからです。
実践効果:
3つ程度にすると、比較しやすく、心理的な負担が軽減されます。特に中間プランは「ゴルディロックス効果」(ちょうどよさ)で選ばれやすくなります。
ランディングページのCTA(ボタン)や選択肢の数
状況:
「無料相談」「資料ダウンロード」「料金を見る」「動画を見る」など、CTAボタンを多く配置しすぎると、ユーザーはどれをクリックすればいいか迷ってしまいます。
理由:
選択肢が多すぎると、ユーザーは“決めること”に疲れてしまい、行動せず離脱してしまうからです。
実践効果:
CTAは1〜2つに絞り、明確な行動導線を作ることで、離脱率が下がり、コンバージョン率が上がります。
飲食店のメニュー設計
状況:
メニューが多すぎると、「何を食べるか決められない」という体験をしたことはありませんか?
理由:
選択肢が多いと、後悔のリスクが増え、「あっちのほうがよかったかも」と迷い続けてしまうのです(決定回避・後悔回避)。
実践効果:
メニューを10種類以内に絞ったり、「人気No.1」などのおすすめを提示することで、迷いが減り、注文率が上がります。
ホームページのサービス紹介ページ
状況:
あれもできます、これも得意ですと複数のサービスを羅列しすぎると、どれが専門なのか分からなくなります。
理由:
訪問者は“自分に合うサービス”を探しています。選択肢が多すぎると、自分が対象かどうかを判断できず離脱します。
実践効果:
サービスをカテゴリ別にまとめたり、「まずはこのサービスから」と導線をつけることで、問い合わせにつながりやすくなります。
なぜ「選ばせすぎない」ことが有効なのか?
このように、選択肢が多すぎると「選ぶこと」そのものがストレスになり、ユーザーは判断を避けてしまいます。
特にネットやスマホ上の情報空間では、情報量が多いだけに「選択疲れ」を感じやすい。
だからこそ、「あえて絞ってあげる」ことが、優しさであり、購買につながる設計でもあるのです。